こんにちは、バルバル先生です。
今回は、僕が**高校・中学のバスケ部顧問として実際に感じた「学力と部活動の深い関係」**についてお話します。
「勉強ができる子=スポーツもできる」なんて、一見関係なさそうに見えますが、実は密接につながっているんです。
学力が高い学校の方が、部活も強い!?
僕はこれまで、高校で3年間、男女バスケットボール部の顧問を担当し、現在は中学校で男子バスケ部の指導にあたっています。
バスケ経験者として、技術的な指導も行う中で、毎年感じていたことがあります。
「偏差値の高い学校ほど、部活動でも結果を出しやすい」
もちろん、全ての例に当てはまるわけではありませんが、部活に特化した学校ではない限り、学力の高い学校の方が勝率が高い傾向にあるのは事実です。
理由①:話を聞く力・理解する力が高い
学力の高い子は、まず「指導者の話をよく聞ける」ことが大きな特徴です。
言われたことをそのまま実行するだけでなく、**「なぜその練習が必要なのか」「どうすれば上達するのか」**を理解しようとします。
その結果、練習の質が高くなり、成長スピードも早い。
ただがむしゃらにやるのではなく、効率よく取り組む姿勢が自然と身についているんです。
理由②:メンタルの強さ=受験を乗り越えた自信
そして何よりも大きいのが、**「自信の有無」**です。
偏差値の高い高校に進学した子どもたちは、
受験という人生で初めての本格的な戦いに勝ってきた経験があります。
✅ 努力は報われる
✅ 自分にはやれる力がある
✅ 困難を乗り越えた実績がある
こうした自信が、試合のプレッシャーの中での冷静さや、最後まで諦めない粘り強さに繋がっていきます。
一方、勉強でつまずいた子は…?
逆に、勉強に苦手意識がある子や、受験に敗れてしまった経験のある子たちは、
自分を信じる力が弱く、チームメイトや指導者に対しても疑念を持ちやすい傾向があります。
「どうせ自分なんて…」
「やっても意味ないし…」
「ミスしたら怒られるし…」
そんな気持ちが無意識のうちに行動に出てしまい、勝っていた試合でも、終盤で焦ってミスを連発→逆転負けなんてことも珍しくありません。
テクニックやフィジカルより、支える“メンタル”の土台が大事
バスケはもちろん、どんなスポーツでも、勝負の分かれ目は「ここぞの場面で冷静に、堂々とプレーできるか」にあります。
それを支えているのが「自己肯定感」。
どんなにテクニックや体力があっても、自分を信じられなければ、その力を発揮できません。
低学力と自己肯定感の低さは、切っても切れない関係
これまでの教育現場での経験からも痛感しているのは、
「低学力」と「自己肯定感の低さ」は深く関係しているということ。
「自分は勉強ができない」
「どうせ何やってもダメなんだ」
「自分には価値がない」
そういった思い込みが強くなればなるほど、勉強も運動も、うまくいかなくなっていく。
まさに負のスパイラルです。
大人ができること:子どもの「自信の根っこ」を育てよう
どちらが先かは一概には言えませんが、
この悪循環を断ち切るには、やはり周りの大人の関わり方が重要です。
✅ 小さな成功体験を積ませる
✅ 頑張った過程を認める
✅ 結果が出なくても「やってよかったね」と伝える
こうした積み重ねが、「努力は報われる」という感覚を育て、
やがてスポーツの場面でも“本番に強い選手”を生み出すことにつながると、僕は信じています。
まとめ:勉強とスポーツの根っこは同じ
勉強も部活も、本質は「できなかったことが、できるようになる」こと。
その喜びを、子どもたちに教えてあげるのが、僕たち大人の役割です。
自信の根っこを育てる指導を、これからも大切にしていきたいと思います。
🌱関連記事
- 低学力高校生の5つの共通点

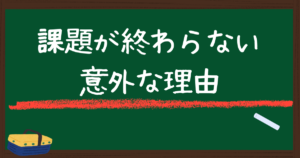

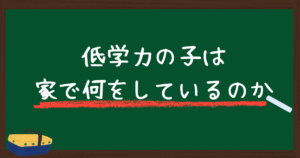



コメント