「先生、うちの子、逆上がりできないんですけど大丈夫ですか?」
これは、小学校の保護者面談でよく聞かれる質問のひとつです。
運動が得意な子どもにとって、逆上がりはちょっとした「目標」や「自信」になります。しかし、実は逆上がりには大きな落とし穴があるのです。
逆上がりの“発達のタイムリミット”とは?
逆上がりに必要な身体能力(腕の引きつけ力・タイミング感覚・体幹の強さ)は、だいたい9歳(小学3年生)くらいまでに発達するといわれています。
つまり、小学校高学年になってから習得するのは、実はとても難しいということ。
にもかかわらず、文部科学省の教育課程では、鉄棒運動として逆上がりが本格的に登場するのは小学校中学年以降。
この「発達のピーク」と「授業での登場時期」のズレが、現場の教師や子どもたちを苦しめている大きな原因なんです。
僕自身、中学までできなかった
じつは、僕自身も逆上がりができるようになったのは中学生になってからでした。
幼稚園の頃から体操教室に通っていたにもかかわらず、何年も何年も逆上がりだけができない。
悔しくて、恥ずかしくて、ずっと「なんで自分だけ…」という思いを抱えていました。
でも、中学校に入り、バスケットボール部に所属して筋力がついてきた頃、ある日ふと試してみたら——
あれ?回れた!
まるで魔法のように、それまで何年もできなかった逆上がりが、突然スムーズにできるようになっていたんです。
身体が追いついていなかっただけ
この経験を通してわかったのは、できない=センスがない、努力が足りない、ということではないということ。
僕は、小さい頃から「逆上がりをする感覚」自体は、練習を通して身についていたんです。
でも、筋力や体格など“体の準備”が追いついていなかった。
華奢な子、大柄な子など、体格によって逆上がりの難易度はかなり変わります。
なので、できなくても焦らなくていい。「感覚」さえ育てておけば、あとから必ず追いつく。
指導する側が知っておきたいこと
- 逆上がりのゴールデンエイジは小学3年生くらいまで
- 発達には個人差があるため「高学年からでも遅くない」子もいる
- 感覚的な練習は、早期から積み重ねることが大切
- 「できた!」という達成感を味わえる仕掛けが必要
できない子どもに「できない理由」を正しく説明し、
「君はまだ体が追いついてないだけだよ」という言葉をかけるだけでも、子どもはグッと前向きになります。
まとめ:逆上がりは“今できるか”より、“いつかできる”が大事
逆上がりは、ただの運動技術ではありません。
その中には、努力・悔しさ・継続・成長といった、たくさんの感情と学びが詰まっています。
「いまはできなくても、きっとできるようになる」
その成功体験が、子どもにとって一生の財産になるはずです。
そして僕も、できなかったからこそ——「できない気持ち」がわかる教師でいられています。
📣 子どもの運動に関する悩み、もっと知りたい方はInstagramでも発信中!
👉 @barubarusensei をチェック!
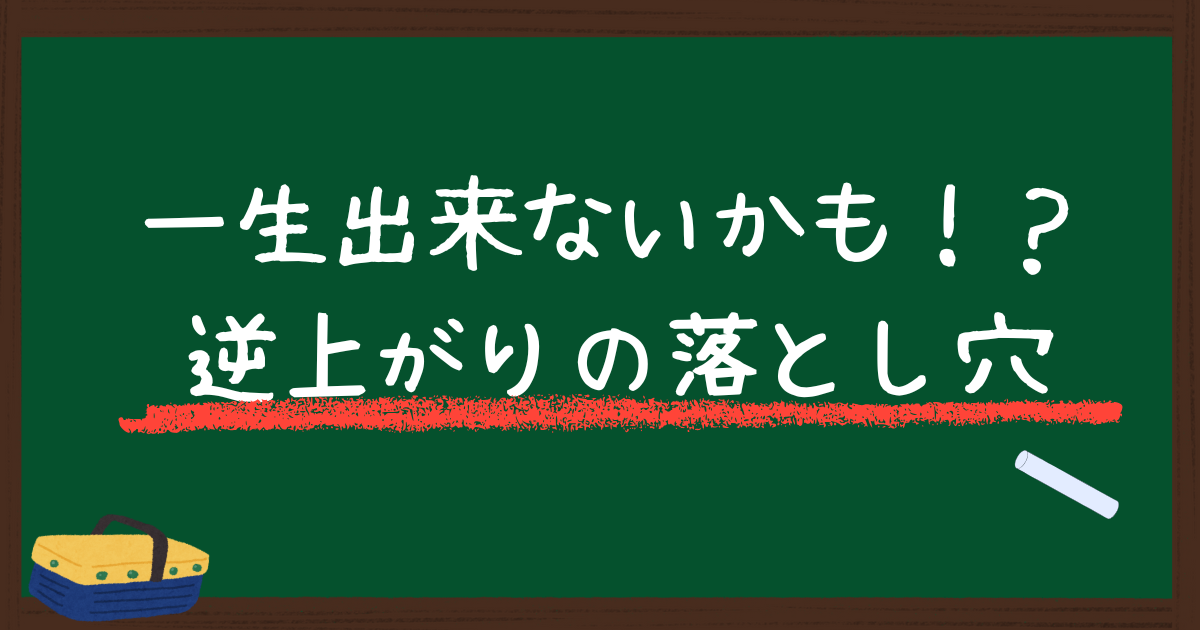
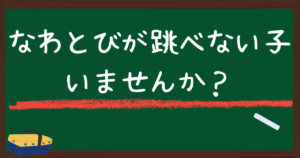
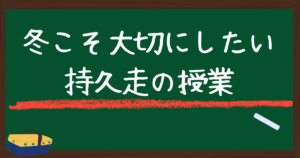
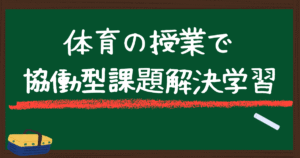

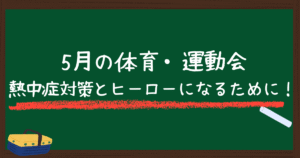


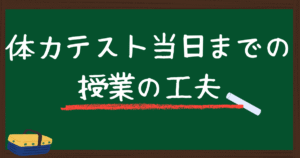
コメント