「どうしてこの子はなかなか成績が上がらないんだろう?」
「頑張っているように見えるのに、伸び悩んでいる…」
教員として日々子どもたちと関わる中で、成績が伸び悩む子どもたちには、**“共通するマインド”**があると感じています。
この記事では、私が現場で見てきた「学力の低い子に共通する5つのマインド」をご紹介します。
早い段階で気づいてあげることが、学力向上だけでなく、自己肯定感の回復や学校生活の安定にもつながります。
1. 自己肯定感が低い
授業がわからない。
テストを返されれば、自分より高い点を取る子ばかり。
居残り、再テスト、補習――。
こうした繰り返しの中で、「自分はできない」「自分なんて…」と自信を失い、自己肯定感が著しく低くなってしまう子が多くいます。
特に高校生になると、受験や内申など現実的な評価が重くのしかかり、深い劣等感につながることも。
2. プライドが高い(でももろい)
意外かもしれませんが、自己肯定感が低い子ほど**「高いプライド」で自分を守ろうとする**傾向があります。
- 授業中に教師のサポートを拒否
- 間違えることを極端に嫌う
- 「挑戦しない」ことで失敗を避けようとする
失敗=劣等感に直結するため、そもそも挑戦しないという選択をするようになります。
3. 謝ることができない
1・2の特徴とも関連しますが、「素直に謝れない」ことも多く見られます。
注意や指導を受けたときに、
- ごまかす
- 言い訳をする
- 逆ギレする
といった反応をする子は、自分の“できなさ”を認めることが怖いのです。
4. 自分の非を認めず、他人や環境のせいにする
- 「ちゃんと勉強したところが出なかった」
- 「テストが難しすぎた」
- 「体調が悪かった」
- 「○○先生の教え方が悪い」
…など、常に“自分以外”の理由で正当化しようとする姿勢が見られます。
この状態では、「次こそ頑張ろう」「やり方を変えてみよう」といった前向きな改善が起こりません。
5. 悪い意味で楽観的すぎる
「提出物が出せなくてもなんとかなる」
「成績が悪くても進級できるから大丈夫」
「テスト?まぁ、次頑張ればいいや」
このように、現状を軽く見てしまう傾向も多く見られます。
特に中学生までは義務教育ですので、出席日数や成績が悪くても進級できてしまいます。そのため、危機感を持たないまま過ごしてしまうことも。
ところが、高校生になると「なんとかならない現実」が一気に押し寄せます。
そのとき初めて、
- 不登校
- 部活を退部
- 学校を退学
- 親を巻き込んだトラブル
といった形で、問題が顕在化することも少なくありません。
◆ 年齢が上がるほど、改善は難しくなる
この5つのマインドは、小学校低学年 → 高学年 → 中学生 → 高校生 と年齢が上がるにつれて強くなり、修正が難しくなる傾向があります。
ですので、1つでも当てはまる子がいれば、できるだけ早い段階で働きかけることが重要です。
◆ おわりに
学力の差は、単に「能力差」だけではありません。
その子の「考え方」や「感じ方」、つまりマインドによって大きく影響を受けます。
今回ご紹介した5つのマインドは、子どもの言動の“裏にある心”を理解するためのヒントです。
周囲の大人がそのサインに気づき、否定ではなく、共感と支援で寄り添うことが何よりのサポートになります。
Instagramでは、現場のリアルや教育のヒントを発信中!
子どもたちの“学力”や“体力”、そして“心”を育てるためのヒントを毎日投稿しています。
フォロー・コメント・DM、大歓迎です!

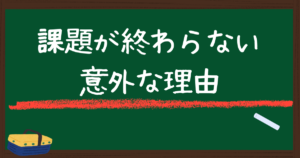
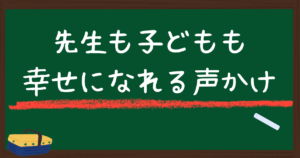
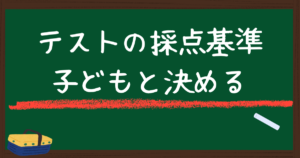
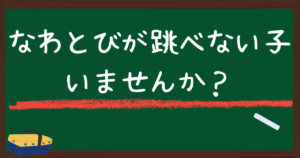
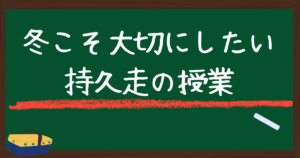
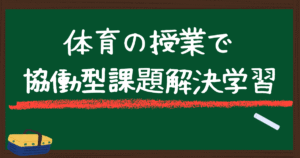
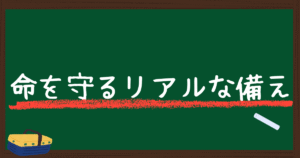
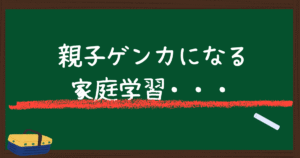
コメント
コメント一覧 (2件)
教師として子どもたちと接する中で、成績が伸び悩む子には共通する心の状態があると感じます。特に高校生になると、受験や内申が重くのしかかり、劣等感を抱くことも多いです。自己肯定感が低い子ほど、高いプライドで自分を守ろうとする傾向があります。失敗を恐れて挑戦しない選択をするため、成長の機会を逃してしまうことも。このようなマインドを理解するためには、どのようなアプローチが効果的でしょうか? WordAiApi
Clusteringさん、コメントありがとうございます!
おっしゃる通り、高校生になると現実的な評価がのしかかり、心のバランスを崩す子も少なくありませんよね。
特に「プライドで自分を守る」傾向は私も日々感じています。
ご質問の「どのようなアプローチが効果的か?」についてですが、
私が意識しているのは以下の2点です👇
①失敗しても大丈夫という空気づくり
→「やってみたこと自体を評価する」ことで、挑戦する勇気を育てます。
② 安心できる小さな成功体験を積ませること
→例えば「今日プリントを全部出せた」「わからないけど前に出て発表した」など、本人の中で小さな成功と感じられるような声かけを意識しています。
この2つは生徒と関わる時間が長かった部活指導で特に効果があったと実感しています。
Clusteringさんの現場でも、どんな工夫をされているかぜひお聞きしてみたいです!